|
「では、授業を始めます。今日は2回目になりますが、先週の1回目の授業を担当された方は、非常に男前のかっこいい T 先生という方だったと思いますが、私はその方と名前が同じだし、しかも顔も非常によく似ていると言われ、もしかしたら双子の兄弟ですかと言われたりするのですが、その人は実は、…私です。」
と言って2回目の授業を始めることにしている。理論的に間違ってはいないと思うのであるが、何人かの学生には受ける。 「確かに先週の私に比べて、今週の私の頭の毛は何本かは少なくなっていますが、紛れも無く私です。すなわち私が私であることには、頭髪の本数は全く関係していないと言うことですね。では、私が私であることは何で決まっているのでしょう?」 ”私” のこの体は、生まれたときのものでは全くない。私の手や足や頭や内臓や、あるいは血液や脳などを作っている物質はほとんど全て入れ替わってしまっているはずである。でも、”私” は生まれたときからズーと ”私” である。ズーと引き継がれてきたもの、つまりそれら物質自体ではなくて、それらをそれらであらしめる関係、あるいはシステムのようなものがある。それが ”私” であるというしかないように思う。すなわち 私とは、この体というハードウェアに刻み込まれたソフトウェアである。 (してみると、パソコンのオペレーティグシステム(OS:コンヒュータを動かす基本ソフトウェア)を Windows から UNIX に変更できるように、ひょっとしてこの体のOSは、今の私から別の私という OS に変更(マインドコントロール)できるかもしれない。まさかそんな簡単なものではないか?) ところで、次のような問題が中学1年の数学の問題集などに載っている。 『Aの容器には10%の食塩水が300g、Bの容器には8%の食塩水が500gある。A、Bからそれぞれ同じ量だけ取り出して互いに他の容器に入れてよくかき混ぜ、AとBの食塩水の濃度が同じになるようにしたい。どれだけの量を取り出して互いの容器に入れればよいか。』 解法としては、取り出す量を  とし、 とし、 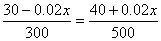 … (*) の方程式を導き、これを解けばよい。 … (*) の方程式を導き、これを解けばよい。
さて、ここで疑問が起こる。この問題はほんとうに数学の問題なのか? 理科の問題ではないのか? この問題を解くということは、 (1) (*)の方程式を導くこと (2) (*)の方程式を解くこと の2つの作業を行うことである。(2)の作業は確かに数学であろうが、(1)の作業は理科である。 数学が対象としているものは、自然現象や社会現象そのものではなくそれらの中にある量的な関係や空間的な関係(構造)である。というより、抽象的な数や図形の間にある関係(構造)である。 また、数学にはいろいろな用語があり、それらの内包すること(概念)は、きっちり定義されている。しかしながら、それら自体が数学ではない。数学はあくまでそれらの間にある関係(構造)自身である。 このような抽象的な数や図形の間にある関係(構造)をそのまま理解することは困難であり、したがってその具体例を自然現象や社会現象に求め、その助けを借りて数学を理解することは、しばしば我々の行なうことである。また逆に、自然現象や社会現象を数学という体系に対応させ、数学の言葉を使って表現したり、あるいは数学というシステムを使って新しい知見を得るのである。 私というソフトウェアを刻み込んだこの身体は、外界からの刺激により日々書き換えられながらも私というアイデンティティーを保持しながら連続的に変化するしかあるまい。 (2002.10.24)
|
**********************************************************************************
Copyright(C) Yokahiyokatoki
 > 『数学的思考(?)エッセイ』 の試み
> 『数学的思考(?)エッセイ』 の試み